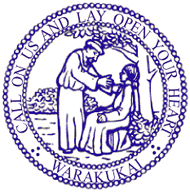![]()
![]() パニック障害治療薬の副作用
パニック障害治療薬の副作用
−知って正しく使えばこわくない−
パニック障害は薬による治療が有効なことが実証されており、医師にとっても患者にとっても幸いなことである。しかし薬には副作用がつきものであり、それを恐れる患者さんが少なくない。少なくないどころか、私の経験では、薬物療法を開始しようとすると、ほとんどの患者さんが心配そうな表情で「副作用はないですか」と質問される。中には口でははっきり言わないけれど、実際にはのまなかったり、適当に減らしてのんでいる人もいる。これでは有効とわかっている薬も効かないし、病気もよくならない。
パニック障害は不安障害の一種なので、患者さんは何事につけても不安・心配をいだきやすく、処方された薬(の副作用)に不安をもつのも無理はない。しかし薬に対する不安は病気のせいばかりではなく、一部のマスコミによる誇張された薬害報道や、医療に対するネガティブ・キャンペーンの影響を受けた結果である場合が少なくない。また患者さん本人は主治医を信用していても、家族や知人などがこれらの影響を受け、「薬なんかあまりのまない方がいいそうよ」「副作用ってこわいのよね」などと、好意の仮面をかぶった無責任な受け売りをする場合が少なくない。患者さんは副作用に対する不安と、周囲からの脅しの両方にうち勝って薬をのまなければならないわけで、これでは安心して薬物療法を受けることが出来ない。
それではどうすれば安心して薬による治療を受けることが出来るであろうか。一つはわれわれ医師が、薬物療法の意義や処方した薬の副作用について患者さんによく説明することである。最近では処方した薬の名前や効能を教えてくれる病院(医師または薬剤師)が増えてきているが、副作用についても積極的に説明する必要があろう。しかし無用な不安を与えても逆効果であり、そのあたりのかねあいがむずかしい。
薬の効能書きには膨大な副作用情報が記載されていて、実状を知らないものが読むと、こわくてとうていのむ気にならないほどである。しかしそのほとんどはまれなものや、特殊な条件下で起こる可能性を記載したものであり、実際には心配ないものである。したがって、個々のケースで必要な情報を選択して患者さんに伝えることが重要であり、その意味で副作用の説明は単なる情報伝達ではなく、まさに治療の一部と言える。後に述べるように、プラセボー(薬効成分を含まない偽薬のこと)でも実薬とかわらぬほどの副作用が出ることがわかっており、副作用の発現には暗示作用(医師の説明、マスコミの報道、友人の助言のどれもがその効果をもつ)の影響が大きい。
次に大切なことは、患者さんも薬について勉強する必要があるということである。勉強と言ってもむずかしい専門書を読む必要はない。医学や薬学の素養のないものが専門書を読んでも理解が困難であり、むしろ逆効果の場合が多いであろう。自分の病気について書かれた一般向けの本(啓蒙書)の中から、適当なものを選んで読む程度でよい。その中に薬物療法のことや薬の副作用のことも書かれており、ほとんどの場合それで十分である。ただし「適当な本」を選ぶには専門家の目が必要であり、それを主治医に相談するのである。パニック障害については、貝谷先生が良い本を何冊も出版しておられるので、その中から選べばよい。
こうして自分の治療薬について一通りの知識を身につけたら、薬を指示通り服用し、その結果どんな効果があったか、なかったか、副作用と思われる症状はどのようなことがあったか、などをありのままに医師に伝えることが重要である。すなわち、薬の服用結果についての情報を正しく医師にフィードバックするのである。医師はそれを聞いてその患者さんにより効果的な薬や用量を見定め、その患者さんに現れやすい副作用に注意し、処方に反映させることが出来る。こうして医師と患者との共同作業で薬物療法が進んで行く。言いかえれば患者も薬物療法の一方の主人公になるということである。副作用の問題もその中で解決されていくことが望ましい。
現在は昔のように「すべて先生におまかせします」式の医療の時代では既になくなっている。だからと言って形だけ「インフォームド・コンセント」(説明と同意)が整っていれば良い医療が出来ると言ったものでもない。医師−患者間の基本的な信頼関係にもとづく共同作業が、情報の氾濫する中で薬の副作用不安にうち勝ち、薬物療法を受ける正しい道である。次回からパニック障害の治療に用いられる主な薬について解説し、副作用とそれへの正しい対処法について述べる。

文責 竹内龍雄
帝京大学医学部精神神経科学教授(市原病院)
ケ セラ セラ<こころの季刊誌>
VOL.13 1998 SUMMER