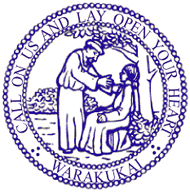|
旧制高校という時代があった。青年が学問を意識しながら自由を謳歌した時代である。教授も学生も細かいことは言わない。授業に出るとか、出席を取るとかそんな野暮なことは言わない。教授も学生もまず人生の真理を考え哲学的な読書を重んじた。夜は高下駄を履き破衣、破帽で町内を闊歩し、よく酒を飲み、議論し、寮歌を歌った。バンカラと言われた。町の人は、そのような若者たちを好意とある種の敬意をもって厚遇した。実際大物が育った。一高は現在の東京大学教養部であり、二高は東北大学教養部であり、三高は京都大学教養部であり、四高は金沢大学教養部であり、五高は熊本大学教養部である。ナンバースクールと呼ばれた。今でも大きな業績を成し遂げた老人達が、旧制高校時代を懐かしみ、当時の格好のままで集まり寮歌祭を開き、肩を組んで大声で寮歌を歌っている。細々した勉強はしなかったが、世界的な学問業績が上がった。このシリーズの第2回に登場してもらった森田正馬は第五高等学校卒である。森田はこの五高であの夏目漱石に英語を習っている。教授も素晴らしかった。その伝統が多少なり残っているのが京都大学である。学問の自由が残り、独創的な研究が生まれている。最も優れた臨床精神病理学者の中井久夫氏は当初京都大学のウイルス研究所で研究していたウイルス学者であった。そんな自由が京都大学にはある。
|
 ケ セラ セラ<こころの季刊誌>
ケ セラ セラ<こころの季刊誌>