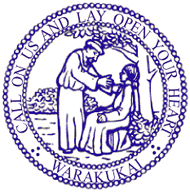|
岩波明氏は筆の立つ精神科医で、現在、昭和大学医学部精神科の准教授です。その岩波氏が昨年「文豪はみんな、うつ」幻冬舎新書176という興味深い新書を出版しました。直ぐ目に留まって購入はしたのですが、その題名の軽さから、本棚に置きっ放しになっていました。今回この連載を書くに当たって何か参考になる事は無いかと目次を見ました。第一章は予想通り夏目漱石に始まり、第十章は川端康成と全部で10名の文豪が取り上げられていました。「小説家の病跡」は私の一つの専門領域ですので、岩波氏とは認識の違いは多くありましたが、私が一人その病に気付かなかった文豪がいました。それが谷崎潤一郎です。私も何冊か谷崎の小説を読み、アルバム集も見ていましたが、谷崎の本能的欲求の強い強力性は感じるものの、不安・うつというイメージは全くありませんでした。あの北大路盧山人のように食に対し、美に対し、女性に対し、そして芸術に対してデーモンのように極めた作家です。その文豪谷崎が小さい頃より晩年まで不安障害があったとは大きな意外でした。今回はこ
ケ セラ セラ<こころの季刊誌> |
|