
医療法人 和楽会
理事長 貝谷久宣
名古屋市立大学医学部の学生時代、病理解剖に興味を抱いていた私が精神科医を目指すことになったのは、当時信州大教授だった精神医学者の西丸四方氏が書いた1冊の本、「病める心の記録」がきっかけだった。ある分裂病の少年の手記をまとめたもので、その内容に深く感銘を受けた私は、精神科医になって分裂病に苦しむ患者を治したいと思った。
ちょうどそのころ、脳の病理学的研究では名の知れた難波益之氏が、岐阜大学医学部神経精神科教授に就任した。そのことを知った私はすぐに教授に会いに行き、初弟子にしてもらうことにした。今から思えば、研究者としては恵まれたスタートだったと思う。
しかし、教授は精神疾患を神経病理学などで科学的に解明しようとする生物学派で、心理学派の研究を続ける助教授らと激しい対立が起こった。このため、私は教授派対助教授派という長年に渡る不毛な"抗争"に自ずと巻き込まれることになった。
そうした不穏な状況で研究を続け10年余が過ぎたころ、医師としての人生観が変わってしまうほどの大きな出来事に直面した。10歳になる長男の嘉洋が、徐々に筋肉が萎縮していく進行性の筋ジストロフィーと診断されたのだ。
自分の子供が若くして亡くなる難病にかかっていることを知り、私と妻は大きな衝撃に打ちのめされた。私は医学の限界を痛感し、医師である自分がいかに無力であるかを思い知った。
それまでは大学で研究に没頭することに医師としての使命感を感じていた私だったが、息子の病気を機に「医師は患者を治さなければ意味がない」と考えるようになった。
そして93年、助教授の肩書きを最後に長い大学生活にピリオドを打ち、名古屋市でクリニックを開業した。
開業直後は、主に分裂病の患者の診療を行っていたが、まもなく転機を迎えることになる。
そのころ私は、突然に起こる激しい発作と強い不安感が主症状である「パニック障害」の治療に関心を持ち始めていて、抗うつ薬を用いる米国の治療法に手ごたえを感じていた。当時日本では、まだこの病気の認知度は低く、ほとんど治療がなされていないのが実情だった。
私はたまたま知りあいになった中日新聞の記者に、パニック障害は適切な診断と薬物治療でよくなることを話したところ、すぐにそのことを紙面に大きく取り上げてくれた。すると大きな反響を呼び、診療所は長年症状に苦しんでいた患者であふれるようになった。
パニック障害の患者が全国から訪れるようになったため、私は97年、友人医師らと共同で東京・赤坂に二つ目のクリニックを開設。東京と名古屋を行き来しながら、同疾患の治療や啓蒙活動に専念した。この数年でパニック障害が社会的に認知されるようになったことをうれしく思う。
振り返ってみると、人生はプラスマイナスゼロになるように出来ているのだとつくづく思う。32歳になった息子は全面介助の重度障害者とはいえ、彼なりに自立し大学生活や米国一周の旅などをエンジョイして前向きに生きている。
この20年の間、息子の病気のことが頭から離れることは一時もなかったが、私が臨床医として一生懸命にやって来れたのは、彼がいてくれたおかげだと思っている。(談)
(日経ヘルスケア21 2002年 4巻 3頁)
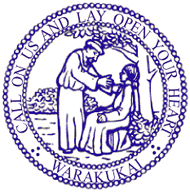
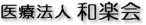

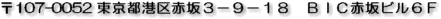

 
|