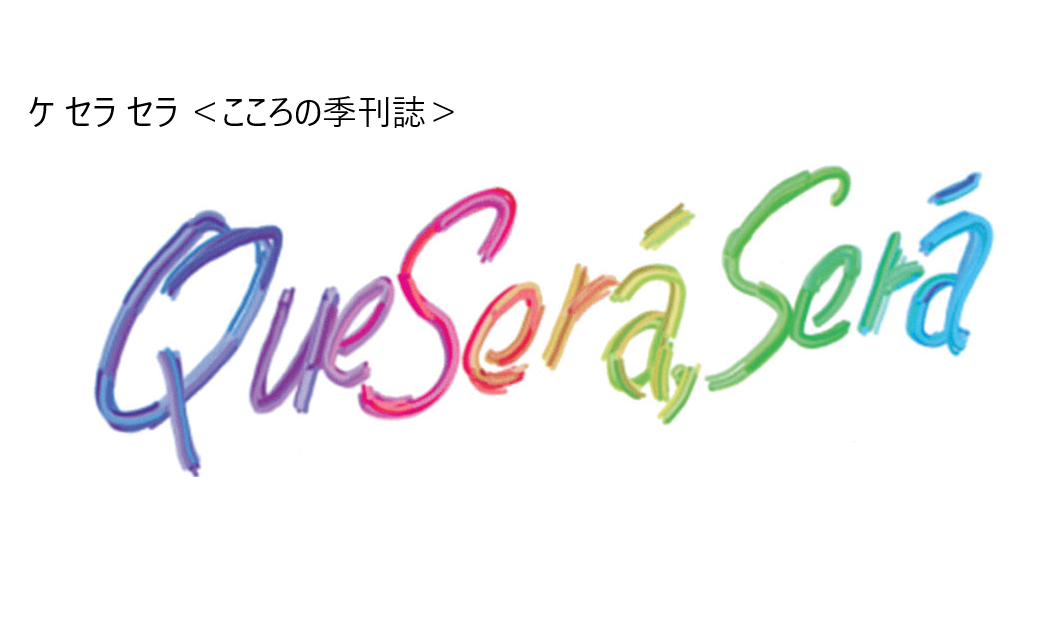
「おばけの声」が教えてくれたこと 〜ある男の子の心の体験記〜(ケセラセラ2025年9月号 vol.139)
医療法人和楽会 理事長 貝谷 久宣
「おばけの声」が教えてくれたこと 〜ある男の子の心の体験記〜
ある男の子が初めて“パニック発作”を経験したのは、まだ小学2年生、8歳の時でした。
朝4時、仲の良い友達が泊まりに来ていたので、早起きして一緒にカードゲームをしていた時のこと。ふいに「死ね」という声が聞こえた気がして、体がふわっと浮くようなめまいが起こり、まるでおばけに襲われたような恐怖に包まれたのです。
慌ててお母さんのところに行き、「ママ、おばけに死ねって言われた」と訴えました。でもお母さんは眠そうに「気のせいでしょ」と言って取り合ってくれませんでした。けれど、吐き気があると伝えると一緒にトイレに行ってくれました。そして、吐いたあと、不思議とスッと気持ちが落ち着いたのです。 このとき、本人は確かに「何かがおかしい」と感じていました。でも見た目には何も異常がないし、周りの人にもわかってもらえず、その後も長い間「気のせい」「わがまま」と言われ続けました。
さらにその後、「死」に関する情報を目にするたびに発作が起こるようになりました。小学生の頃、ニュースでBSE(狂牛病)が話題になった時には、「自分もなるんじゃないか」と思い込み、パニックになって泣き叫んだこともありました。
親もどう対応すればよいかわからず、「救急車呼ぶ?」と困り果てるしかありませんでした。そんな中、初めて心療内科を受診し、「認知療法」や「抗不安薬」を知ることになります。そして、不安の中心にある「脳が悪くなっているのでは」という思いを、MRIで“異常なし”と確認してもらえたことで、少しずつ落ち着けるようにもなりました。
もう一つ印象的だったのは、小学6年生の頃、貧血で体調が悪くなった時のことです。運動中のめまいは平気だったのに、ふだんの生活でめまいが起きると「また脳の病気では」と怖くなってしまうのです。
この不安を、思い切ってかかりつけの医師に話したところ、その先生はこう言ってくれました。
「呼吸が乱れてるね。舌と脈を見せてごらん。一度、心療内科に行ってみようか。次はお母さんと一緒に来てね」
この言葉が、彼の人生を変える最初の大きな転機になりました。先生は、これまで誰にも伝わらなかった“得体の知れない不安”をちゃんと受け止めてくれたのです。その後紹介された心療内科で「不安障害」と診断され、「こういう病気がある」と自分でも理解できるようになったことは、本人にとってとても大きな安心につながりました。
このお話から、私たち親が学べることはたくさんあります。
彼が最終的に「パニック症」と正式に診断されたのは、なんと28歳になってからでした。子どもが「怖い」「気持ち悪い」「頭が変」と言っても、見た目には元気そうに見えると、つい「大げさにしないで」と流してしまいがちです。でも、子どもが必死で助けを求めている時、言葉ではうまく説明できない“心の不安”が隠れていることがあるのです。
本人でさえ「なんでこんなに怖いんだろう」とわからず、もがいているのです。だからこそ、子どもの言葉や態度の裏にある「心の叫び」に耳を傾けてあげること。それだけで、子どもが安心できる居場所を感じ、「自分はおかしくないんだ」と思えるきっかけになります。
この体験記を書いたAさんは、筆者のクリニックを受診するまで適切な治療を受けずに苦しんできました。でも同じようにパニック症に悩む子どもたちは、きっと今もたくさんいるはずです。
パニック症が疑われる子どもの特徴を再度示しておきます。
① 突発性の自律神経症状(吐気、めまい、立ち眩み、頭痛、腹痛など)
② 病気に対する著明な恐れ
③ 別れに敏感
④ 慣れ親しんだものや状況から離れるのが辛い
⑤ 安全の再確認を要求する
⑥ 刺激性の飲み物や食品に過敏(におい、味、不快な音)
⑦ 限局性恐怖症の既往(暗闇、高所、虫、注射)
以上のうち3つ以上当てはまる子はパニック症になる確率が高いと考えられます。
もしあなたのお子さんが、「吐き気がある」「なんだかおかしい」「死ぬかもしれない」「怖い」と訴えることがあったら、どうかその心の声をまっすぐに受け止めてあげてください。
子どもの不安症は発達障害より多いのです。心当たりのある方は一日も早くあなたの大切な子供さんに救いの手を差し伸べましょう。
(この手記は患者さん御本人の了解を得て掲載いたしました。)

